
今日の400字は借名取引(仮名取引)について。
新NISAでは一人当たり1800万円の非課税枠が定められているため、それより多くの資産をお持ちの方の中には「投資してない家族にNISA口座開設させて二人分使っちゃおう」と考える人もいます。
しかしそれは借名取引として明確に禁じられています。
ただ禁じられている程度の言い方では「バレなきゃいいんでしょ、バレなきゃ」と言われそうなのでしっかり詰めておきましょう。
「犯罪収益移転防止法」の響きが持つパワー
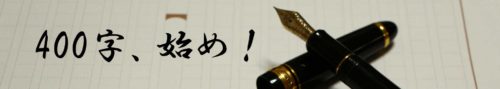
借名取引が禁じられているのは金融機関のハウスルールではない。
犯罪収益移転防止法によって法律として禁じられているのだ。
このワードの意味するところは誰が聞いてもイメージ付くのではないだろうか。
簡単に言うとマネーロンダリングを防止する法律だ。
安易な借名取引で犯罪収益移転を疑われるとどうなるか。
金融庁の資料を引用しよう。
Ⅰ 疑わしい取引の届出制度
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)の規定により、金融機関等は、顧客から収受した財産が犯罪収益若しくは、テロ資金である疑いがある場合又は顧客がその取引でマネー・ローンダリングを行っているのではないかと疑われる場合には、速やかに行政庁に届出を行わなければならない義務が課されている。
疑わしい取引に関する情報は、主務大臣を通じて国家公安委員会に集約されたのち、整理・分析が行われ、犯罪捜査等に資すると判断された情報については捜査機関等に提供されている。
出典:金融庁「第16章 疑わしい取引の届出制度」P1
このような仕組みは「疑わしい取引の届出制度」と呼ばれており、マネー・ローンダリング対策の柱として、我が国のみならず諸外国でも同種の制度が設けられている。
疑わしい取引とみなされたら金融機関から直ちに関係省庁へ届出が行われるだけでなく、場合によっては捜査機関にすら提供される。
金融機関「こらっ!ダメだろ」
顧客『すいやせん、てへへ』
ぐらいで済む話だと思ったら大間違いなのだ。
1.届出の状況
2018年1月から12月までの1年間に、金融機関等から417,465件(前年比17,422件増)※の疑わしい取引の届出が行われた。
出典:金融庁「第16章 疑わしい取引の届出制度」P1
※「平成30年警察庁犯罪収益移転防止対策室犯罪収益移転防止に関する年次報告書」より
同資料によると2018年は41万件もの疑わしい取引があったそう。
うかつに手を出すとそのうちの1件になってしまう恐れがある。
もし周りに借名取引を目論んでいる人がいたら、きちんと犯罪収益移転防止法の名前を出したうえで止めてあげよう。
面倒なら当記事に丸投げしてくれれば幸いだ。
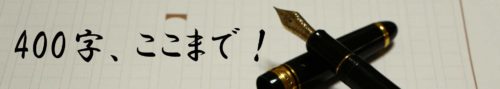
【次回予告】さーて、次回の愚者小路さんは

愚者小路です。
ファンドの口数や金額の計算は要点押さえれば簡単に理解できるもの。
でも苦手な人やすぐ数式がすっぽ抜けてしまう人が一定数いるのも事実。
なら備忘録として簡単ながらまとめておきましょうか。

ありがとうございます。
次回もまた見てくださいね。
応援していただくとより多くの方にご覧いただけるし、投稿モチベーションも上がります。
↑いつもランキング向上にご協力ありがとうございます!
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
・・・なんて機能はないけれど、本件と関連が深い記事です。
もう1ページ、いかがですか?

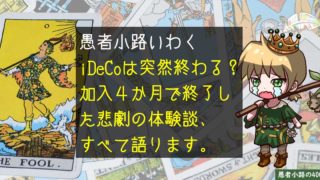
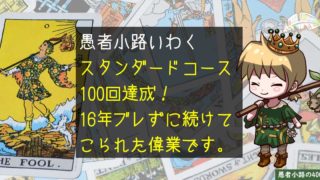
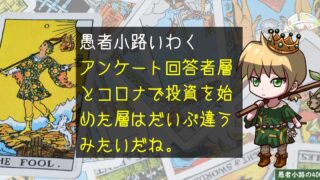
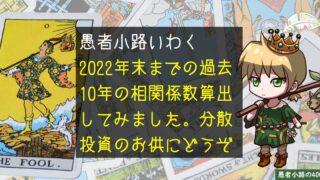
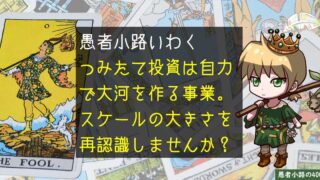
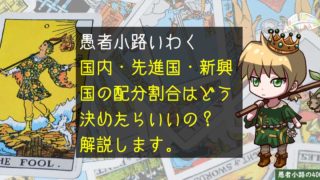
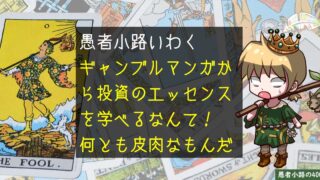
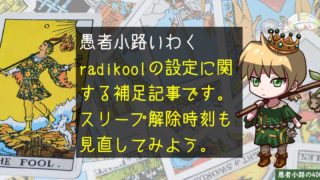
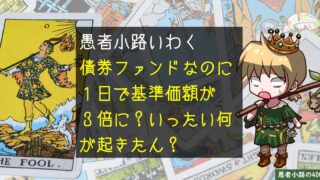
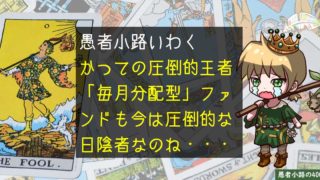

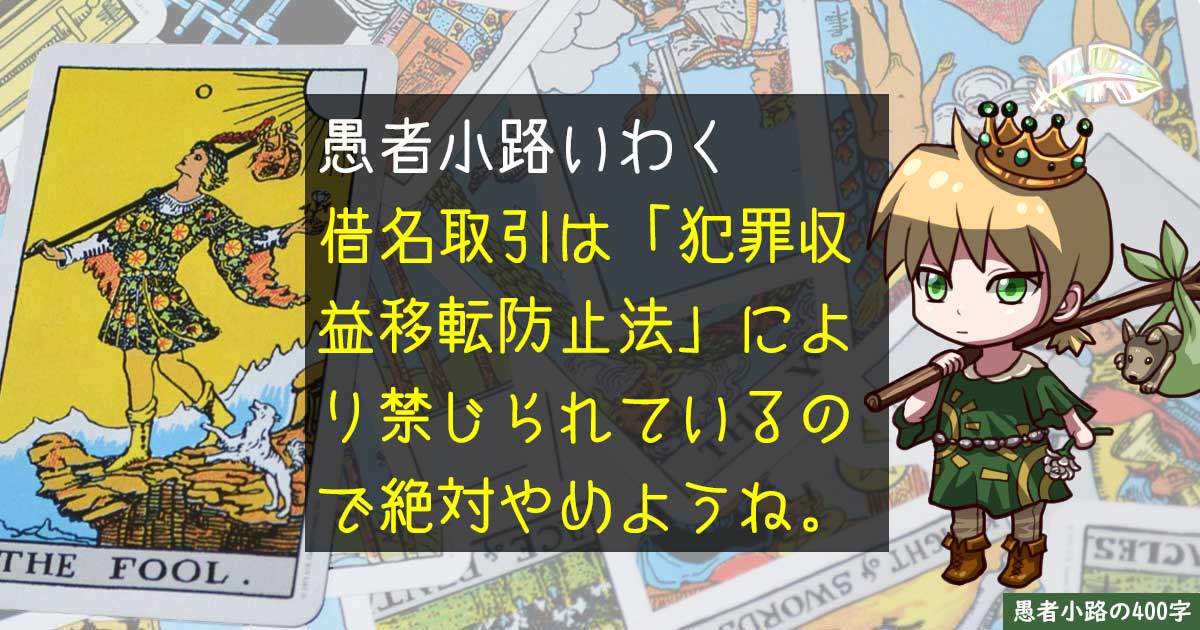
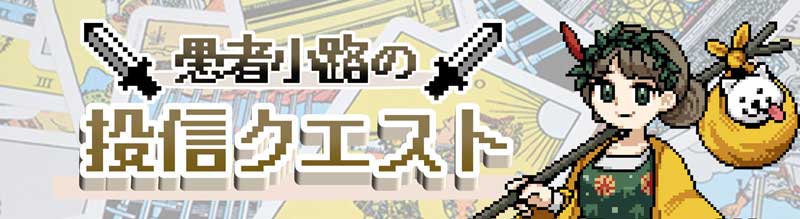

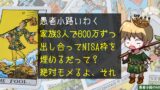
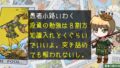

コメント